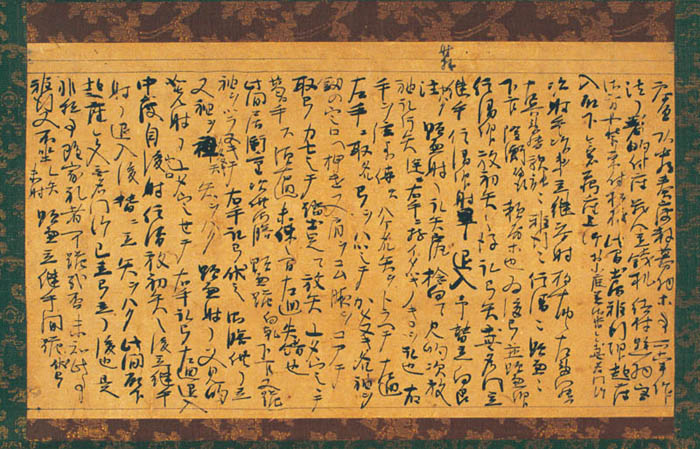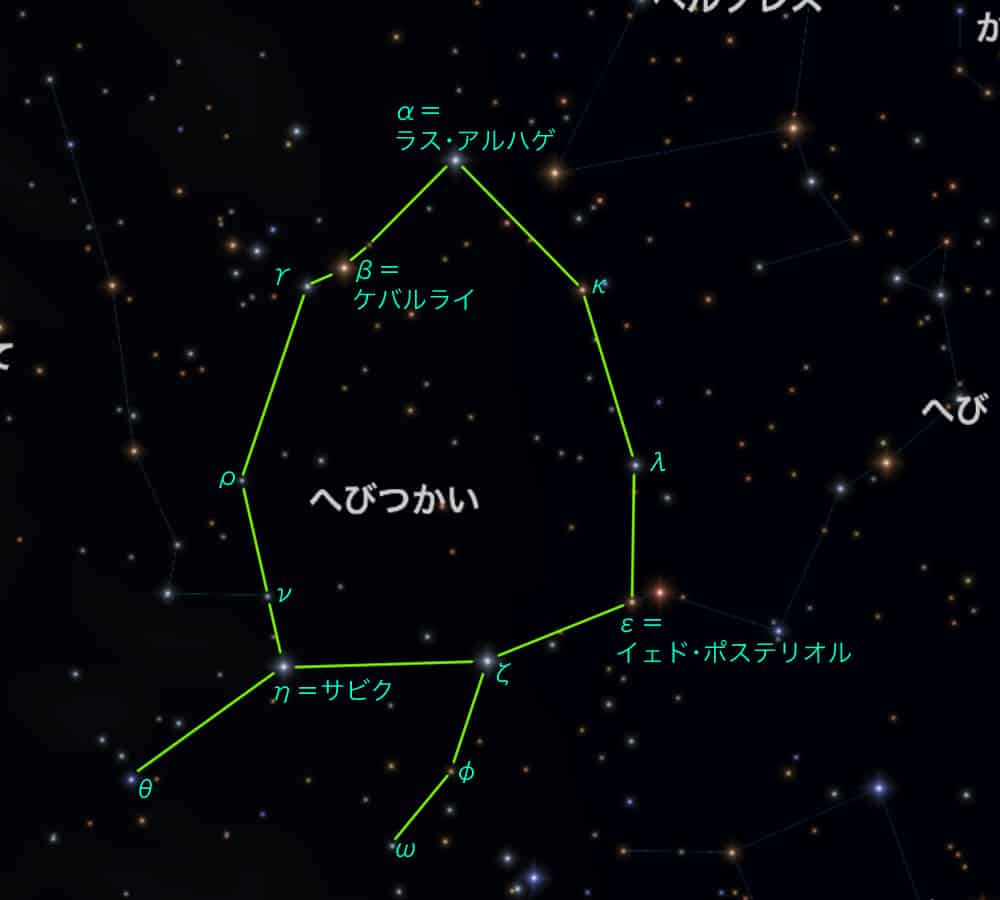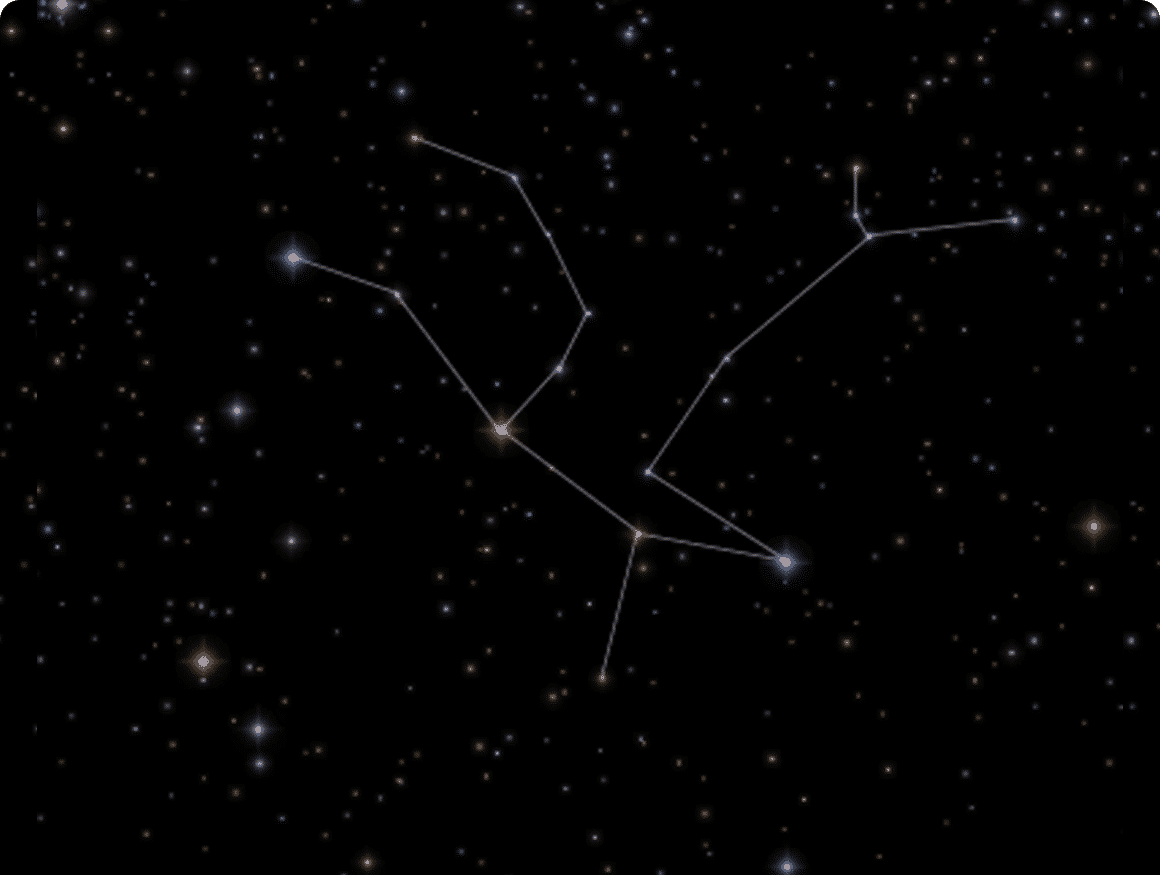
大星雲(アンドロメダ銀河)など、
見つけ方などについてまとめています。
スポンサードリンク
アンドロメダ座の特徴について 銀河や恒星の名前を解説
ですね!
アンドロメダ銀河は、
肉眼でも見ることができる渦巻銀河
とても人気のある天体です。
銀河なのに大星雲とも呼ばれているのは、
混同されていたため、その名残りです。
別名(!?)がありますが、
”シャルル・メシエ”の頭文字です。
星雲・星団などのカタログを作成しており、
31番、という意味です。
といわれています。
2番目がM110です。
小さな銀河のことです。
何とも壮大なスケールですね!
スポンサードリンク
クリックで拡大します
α星・・・アルフェラッツ:2等星
”馬のへそ”という意味だそうで、
ペガスス座の星とともに、
”秋の大四辺形(ペガススの四辺形)”
を、形作る星の一つです。
ペガスス座 秋の大四辺形の動き 方角と位置(高度)による探し方
β星・・・ミラク・2等星
アラビア語で”腰”の意味を持つ。
γ星・・・アルマク・2等星
オレンジとグリーンの二重星。
の意味を持つ。
S星・・・アンドロメダ銀河の中にある超新星。
カシオペヤ座を目印にしてください。
アンドロメダ座があります。
見えなくもないです^^;)
ちょうど天頂に位置しています。
アンドロメダ座の見つけ方 方角と位置を月毎、時間帯別に解説
関連記事
アンドロメダ座の神話 カシオペア座とペルセウス座との関係は?
カシオペア座の特徴と恒星の名前 神話と周りの星座の物語
ペルセウス座流星群とは 特徴と仕組み 放射点の方角と探し方
スポンサードリンク