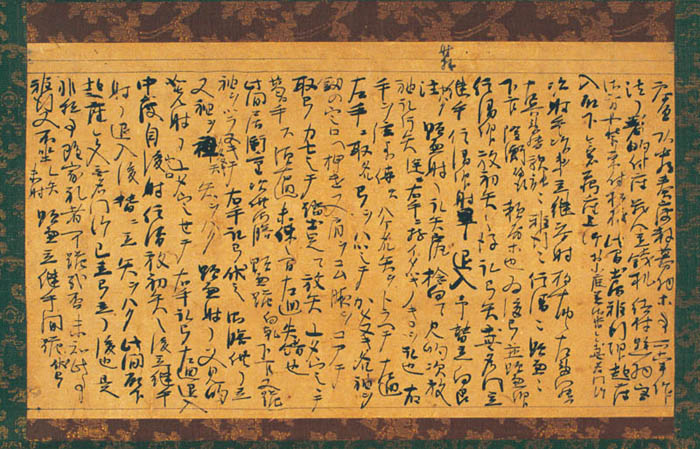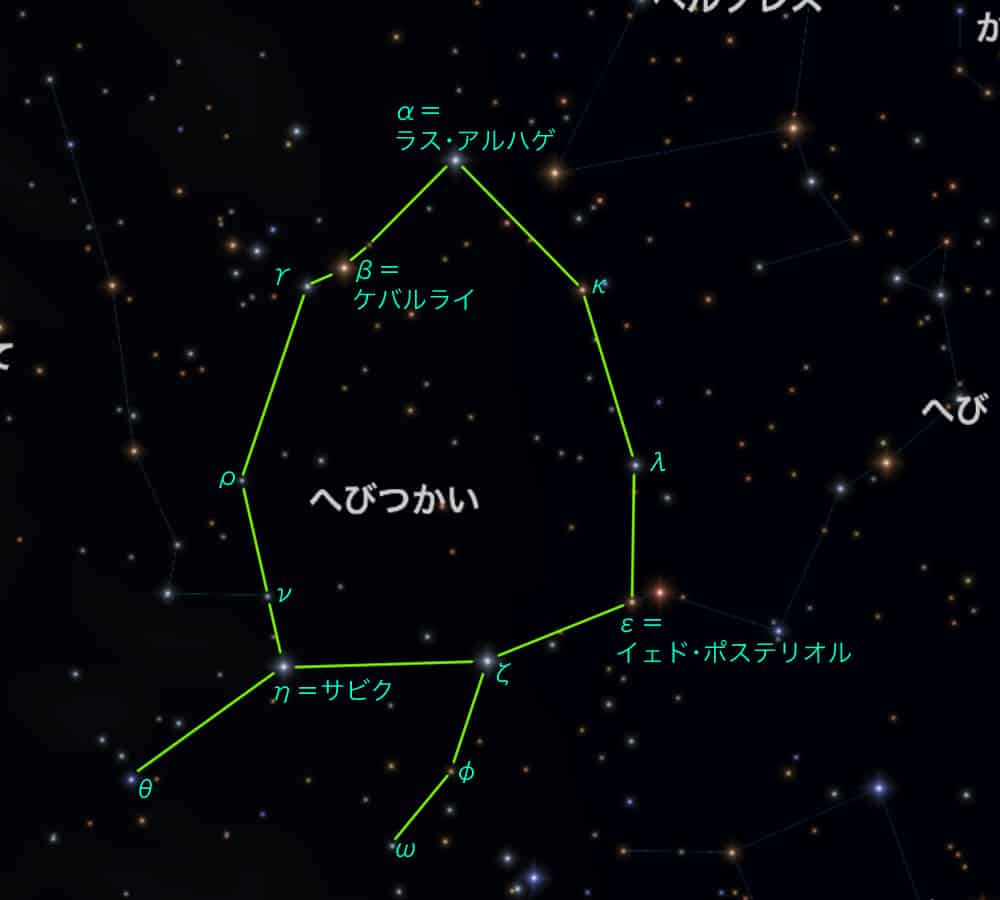わし座の方角や見つけ方など、
まとめました。
スポンサードリンク
Table of Contents
わし座とは 特徴と星の名前
別名を牽牛星(彦星)、
こと座ベガの神話 わし座アルタイルとの2つの牽牛織女伝説
夏の大三角とは 星の名前と星座 方角や見つけ方 動きなど
次に、わし座の主な恒星を見ていきましょう。
クリックで拡大します
こちらをご覧ください ⇒ 脈動変光星とは
わし座の星雲・星団
どんな星雲や星団があるんでしょうか?
2つの惑星状星雲があります。
2つの散開星団と、
散開星団とは 球状星団とは
スポンサードリンク
わし座の方角と見つけ方
追っていきたいと思います。
3月中旬
夜中の3時半ごろ、東の地平より昇ってきます。
観測できるでしょう。
高度30°のところにあります。
4月中旬
日が変わる頃に東の地平より昇ってきます。
午前4時半くらいまで観測可能でしょう。
ところにあります。
5月中旬
午後9時半ごろ、東の地平より昇ってきます。
高度約60°のところにあります。
6月中旬
午後9時ごろ、東の地平より昇ってきます。
日が変わって、夜中の2時ごろに南中します。
高度約50°のところにあります。
7月中旬
高度約10°のところにあります。
高度約60°のところにあります。
高度約30°のところにあります。
8月中旬
高度約30°のところにあります。
高度約60°のところにあります。
午前4時ごろ、西の地平に沈みます。
9月中旬
南東の空、高度約50°のところにあります。
南中は午後8時ごろ(高度約60°)
午前2時半ごろ、西の地平に沈みます。
10月中旬
南南東の空、高度約60°のところにあります。
南中は午後6時ごろ(高度約60°)
日が変わる頃には西の地平に沈みます。
11月中旬
南中時の観測は出来ません。
余程開けた場所でないと観測は難しいでしょう。
午後10時過ぎには西の地平に沈みます。
9月中旬では午後7時ごろに
少し東に視線を移したところにありますが、
関連記事
わし座アルタイルの意味と由来 色と大きさはどのくらい?
こと座 ベガの色や大きさ、アルタイルとの距離と位置は?
わし座とアルタイルの神話 ゼウスとガニュメデス、大鷲について
スポンサードリンク