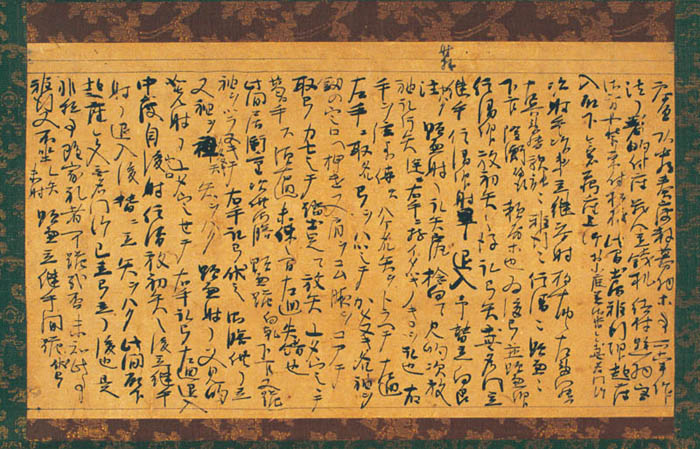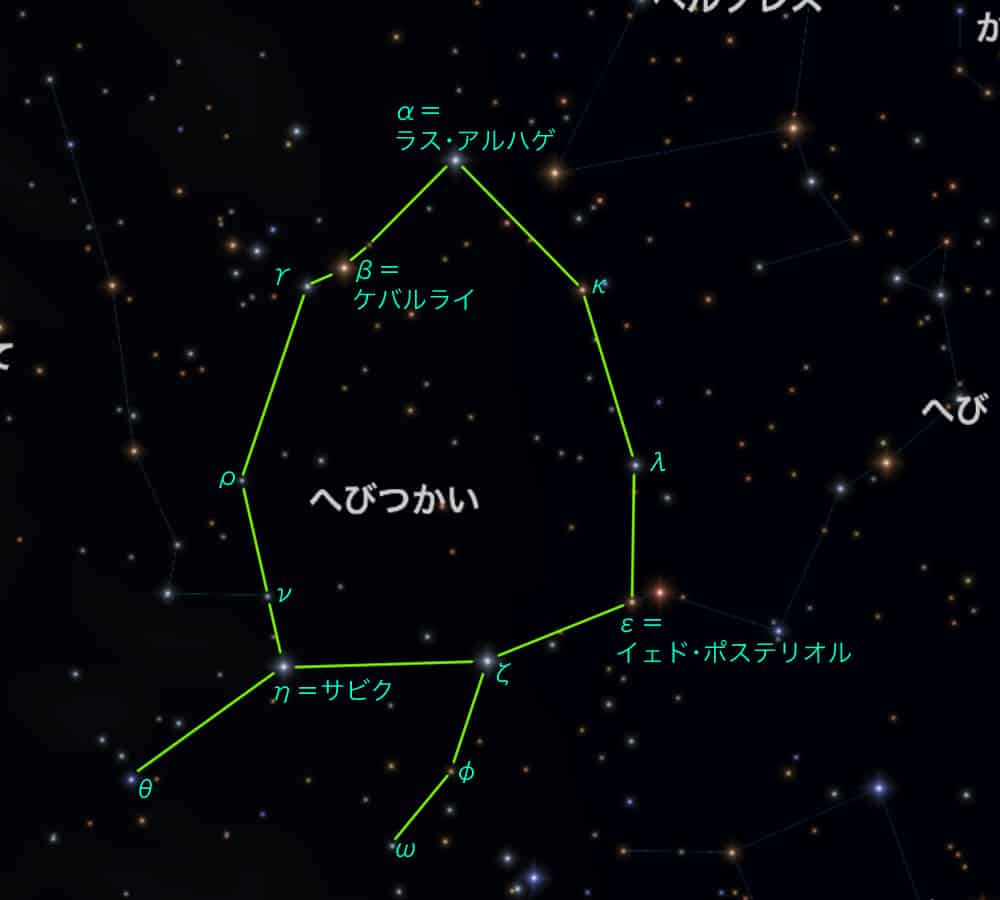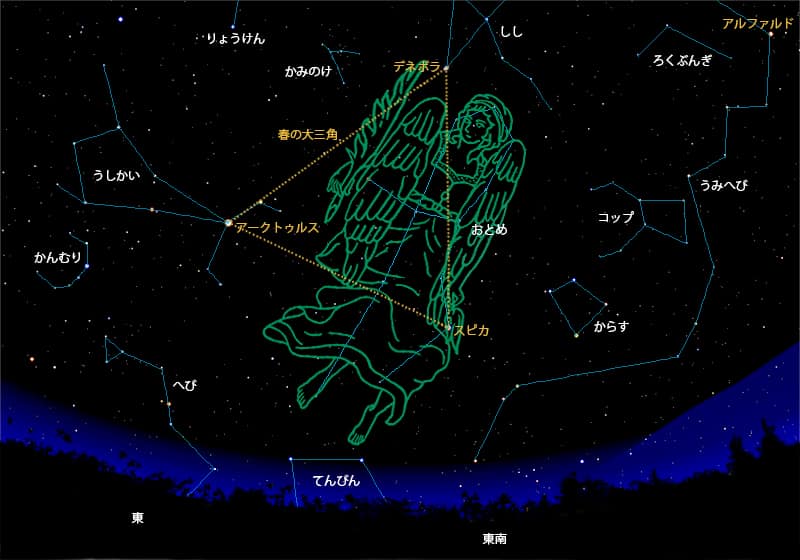
黄道十二星座の一つで、
おとめ座を構成する主な恒星
見つけ方なども記しました。
スポンサードリンク
Table of Contents
おとめ座とは 主な恒星について
トレミーの48星座の一つでもあります。
星の一つとしても有名です。
春の大三角とは 星の名前と星座 見つけ方は?
春の大曲線とは 星座と星と探し方 観測しやすい時期と方角
主な恒星から見ていきましょう!
クリックで拡大します
春の大曲線の途中にある。
春の大三角とは 星の名前と星座 見つけ方は?
春の大曲線とは 星座と星と探し方 観測しやすい時期と方角
β星・・・ザヴィヤヴァ:4等星
女神のうちの一柱:ポリマより命名された。
δ星・・・ミネラウバ:3等星
の意味を持つ。
ζ星・・・ヘゼ:3等星
η星・・・ザニア:4等星
の意味を持つ。
次の章では、
おとめ座超銀河団について
説明していきたいと思います。
スポンサードリンク
おとめ座銀河団とおとめ座超銀河団の違いについて
おとめ座銀河団とは、
クリックで拡大します
約1,500万光年の大きさの中に、
集まっているそうです。
などがあります。
M87の中心にあります。
ブラックホールとは その正体と仕組み・成り立ちについて
ブラックホールの種類 大きさや構造・性質について
約6,000万光年。
先程から出てきてますが、
おとめ座超銀河団はさらにBIGです!
おとめ座超銀河団とは、
大きさは約2億光年!
含まれているんです!!
大マゼラン雲などから形成される局部銀河群も、
おとめ座超銀河団の中に含まれています。
呼び分けているんですね!
ついていけません^^;
おとめ座の見つけ方
北斗七星の柄杓の柄を起点とした、
手っ取り早いと思います。
上図のように、
弓なりに伸ばしていくと、
うしかい座のアークトゥルスです。
それが、おとめ座のスピカです。
春の大曲線の探し方 見える時期と方角 月ごとの動きのまとめ
全天で16番目に明るい1等星なので、
比較的見つけやすいと思います。
春の大曲線などを元に、
見つけてみてくださいね!
関連記事
おとめ座の見つけ方 方角や位置・南中高度など、ひと月毎の動き
おとめ座のギリシャ神話 デメテルとペルセフォネ・アストレアの伝説
しし座とは 星座の特徴と主な恒星 方角や見つけ方は?
スポンサードリンク